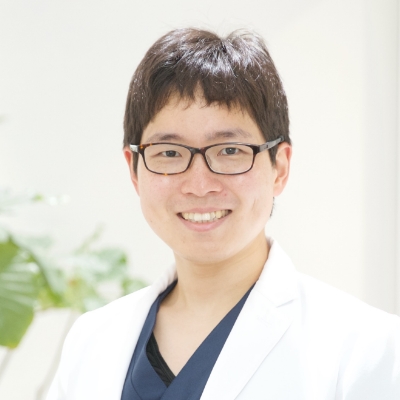うつ病といびきの意外な関係性~睡眠時無呼吸症候群とうつ病の治療法~
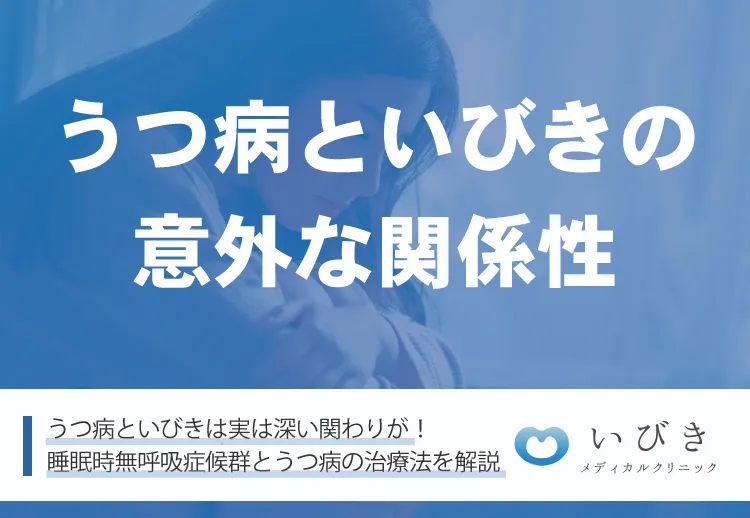
目次
いびきとうつ病は一見関連性がないように思えますが、実は深い関わりがあることをご存知でしょうか。
いびきが原因でうつ病になるケースや、うつ病の治療が原因でいびきをかくケースがあります。これらのメカニズムを理解したうえで、対処法を考える必要があります。
そこで本記事では、いびきとうつ病の関係性や、いびきが引き起こす睡眠時無呼吸症候群の可能性について探っていきます。さらに、睡眠薬や抗うつ剤による副作用やさまざまなリスクについても、詳しく解説します。
うつ病やいびきに悩む方々、支えるご家族に向けて、適切な治療法や注意すべきポイントについてもご紹介していますので、是非最後までお読みください。
うつ病といびきの関係

実はいびきとうつ病は、相関関係にあります。
先述したように、いびきが原因でうつ病になるケース、うつ病の治療が原因でいびきをかくケース。いびきとうつ病は、どちらも互いに影響を与えているのです。まずはいびきとうつ病の関係について解説します。
うつ病の基礎知識
うつ病とは、一日中気分が落ち込んだり、理由もなく悲しくなったりする精神疾患です。うつ病を発症する原因は特定されていません。脳内の神経物質セロトニンとノルアドレナリンが減少して、精神的に不安定になると考えられています。
うつ病の代表的な症状には、気分の落ち込みのほか、不眠症状や無気力感、興味や喜びの喪失、食欲低下などがあります。身体的な症状としては、頭痛や腹痛、吐き気、めまいなども挙げられます。
よくあるのは、過剰なストレスがうつ病を発症したという指摘です。しかし、一般的には嬉しい出来事であっても、うつ病を発症するケースがあります。たとえば、進学や就職、結婚などです。
さらに、身体的な病気や薬の副作用から、うつ病となるケースもあります。思うように身体が動かないストレス、治療への不安、薬の副作用による不快感などが積み重なって、精神的ダメージを与えていると考えられます。
参考:
うつ病|こころの病気について知る|ストレスとこころ|こころもメンテしよう ~若者を支えるメンタルヘルスサイト~|厚生労働省
うつ病|病名一覧|精神疾患・精神病の種類|新宿うるおいこころのクリニック
いびきがうつ病に与える影響
いびきをかくと、睡眠の質が低下します。たとえ8時間の睡眠時間を確保していても、質が低い睡眠では疲れが取れず、充分に回復できません。
そもそもいびきの原因は、口蓋垂や軟口蓋、舌根などが喉の奥に入り込み、気道を塞ぐためです。気道が狭くなるため、たくさんの酸素を取り入れようと、呼吸が激しくなります。すると、狭い気道に勢いよく空気が通るため、いびきとなって大きな音を発生させるのです。頻繁にいびきをかく睡眠では、気持ちよく朝を迎えられません。
睡眠の質が低下すると、日中の疲れが十分回復できず、蓄積された疲れは、うつ病を引き起こしたり、うつ病の症状を悪化させたりしてしまいます。
うつ病患者のいびきはとくに注意が必要
いびきが原因で睡眠の質が低下すると、日中の集中力や注意力が低下する可能性があります。うつ病患者は元々気分が沈みがちで、睡眠不足や質の低下によってさらに集中力や注意力が低下すると、日常生活に支障をきたすことがあります。
いびきの原因や対策についてより詳しく知りたい方は、下記記事をご覧ください。
うつ病と睡眠時無呼吸症候群の関係

うつ病と睡眠時無呼吸症候群は密接な関係にあります。睡眠時無呼吸症候群は、うつ病のリスクを高める可能性があるからです。
ここでは、うつ病と睡眠時無呼吸症候群との関係性や、影響について詳しく解説します。
睡眠時無呼吸症候群とは?
睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に一時的に呼吸が止まる症状です。睡眠時無呼吸症候群のおもな症状としては、大きないびき、熟睡感の欠如、夜間の頻回な目覚め、朝起きたときの頭痛や喉の渇きなどが挙げられます。これらの症状によって十分な睡眠を取ることができず、日中の眠気や疲労感が生じていきます。
睡眠時無呼吸症候群は、おもに以下2つのタイプに分類されます。
- 【閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)】
気道の一時的な閉塞によって呼吸が止まる症状です。口蓋垂や軟口蓋、舌根などが落ち込み、気道を塞ぐために起こります。 - 【中枢性睡眠時無呼吸症候群(CSA)】
脳の呼吸中枢の異常によって呼吸が停止する症状です。脳が呼吸の制御をうまくおこなえないことが原因です。
さらに、睡眠時無呼吸症候群は重篤な病気に繋がる可能性があります。無呼吸状態の継続により、高血圧や心臓病、糖尿病などの合併症のリスクを高めるからです。
睡眠時無呼吸症候群には適切な治療が必要とされるため、症状が疑われる場合は、速やかに医師の診断を受けましょう。
おもな治療法としては、CPAP(シーパップ)療法や外科手術、レーザー治療などがあります。
睡眠時無呼吸症候群の治療方法については、下記記事にも掲載されているのでご覧ください。
睡眠時無呼吸症候群がうつ病を引き起こすメカニズム
睡眠不足は、脳内の神経伝達物質のバランスを乱し、うつ病の発症を引き起こす可能性があります。睡眠中に無呼吸状態に陥っている睡眠時無呼吸症候群は、ただいびきをかいている状態よりも更に大きく睡眠の質を低下させ、重度の睡眠不足を引き起こしてしまう可能性が高いです。
うつ病患者が睡眠障害を併発しやすい理由

うつ病患者は、心身の症状により、睡眠障害を併発しやすいです。うつ病は、セロトニンやノルアドレナリンなどの神経伝達物質のバランスが崩れることで引き起こされることがあります。これにより、睡眠の質が低下し、眠りが浅くなることがあります。また、うつ病自体が睡眠リズムを乱すこともあります。そのため、うつ病患者は睡眠障害を併発しやすい傾向があります。
うつ病患者は生活習慣病にかかりやすい
うつ病患者は、精神的なストレスやうつ病自体の症状により、生活習慣が乱れやすくなっています。
たとえば、意欲の低下から運動不足になったり、食欲の低下から不規則な食生活になったり。タバコやアルコール量が増加する人もいるでしょう。仕事や学校を休む日が続くと、就寝・起床の時間も不規則になりやすいです。
総じて、うつ病の患者さんは生活習慣が悪化しやすい環境にあります。生活習慣の乱れは、生活習慣病のリスクが高まります。うつ病は、高血圧や糖尿病などの生活習慣病を引き起こす要因となるため、とくに注意が必要です。
セロトニンの減少が睡眠時無呼吸症候群を引き起こす
セロトニンは、眠気を誘発する物質です。不足すると眠りにくくなることが知られています。うつ病患者は、セロトニンの分泌が低下していることがあり、これが睡眠不足を引き起こす要因になることがあります。また、セロトニンは、精神的な安定感や落ち着きをもたらすほか、上気道を広げる筋肉を刺激する作用も持っています。セロトニンが不足すると、睡眠中に上気道を広げられず、いびきや睡眠時無呼吸症候群を発症しやすくなってしまいます。睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に一時的に呼吸が止まる症状であり、うつ病患者にとっては注意が必要な合併症の一つと言えます。
睡眠時無呼吸症候群に関する詳しい情報については下記記事をご覧ください。
うつ病と睡眠障害を併発している場合の治療法

うつ病と睡眠障害を併発している場合は、専門医の診断を受けましょう。うつ病と睡眠障害は相互に影響しあうことが多く、適切な治療が必要です。自己判断での服薬や、生活習慣の改善などは、かえって逆効果となる可能性もあります。精神科や診療内科を受診し、正しい治療を受けましょう。うつ病を適切に改善するためには、ひとりひとりに合った治療法を見つける必要があります。丁寧にヒアリングしてくれ、さまざまなアプローチ方法を提案してくれるクリニックを探しましょう。当医療法人の東京にある心療内科の「新宿うるおいこころのクリニック」では、患者さんそれぞれの症状や状態に合わせて最適な治療法を提供しています。
ここからは、うつ病と睡眠障害を併発している場合の一般的な治療法を紹介します。
充分な休養
睡眠障害を改善するためには、充分な休養が必要です。学業や仕事が負担になっている場合は、休学や休職を検討しましょう。決して焦らず、心身の休養だけを考えます。
また、毎日規則正しい生活リズムを作り、睡眠時間を確保しましょう。予定がなくても決まった時間に寝起きします。夜更かしは厳禁です。また、寝る前にリラックスするための工夫や、寝室の環境整備も重要です。
生活習慣の改善
生活習慣の改善も重要な治療法の一つです。適度な運動やバランスの取れた食事、ストレスを溜めない工夫などが睡眠障害の改善につながります。どんな生活習慣を改善すべきかわからない場合は、精神科や心療内科で相談してみましょう。当医療法人の東京にある心療内科の「新宿うるおいこころのクリニック」では、生活習慣の見直しをサポートしています。
心理療法
うつ病や睡眠障害の治療には、心理療法も有効です。心理学的なアプローチで、うつ病の症状を改善するものです。うつ病患者の思考や行動パターンを把握し、問題のある思考や行動パターンを改善させて心の回復を目指します。
代表的な心理療法には、以下のようなものがあります。
- 【認知行動療法】
患者のネガティブな思考パターンを変え、感情や行動を改善する治療法です。具体的な課題や行動実験を通じて、患者自らによる思考の客観的見直しを促します。 - 【インターパーソナルセラピー】
人間関係に焦点を当てた治療法です。人間関係の問題がうつ病の原因や悪化要因となっている場合に効果的です。コミュニケーションスキルの向上や人間関係の改善を目指します。 - 【精神分析療法】
潜在意識や無意識の心理的な要因を探求し、うつ病の原因や症状に影響を与えている要因を理解する治療法です。過去の経験や関係性に焦点を当てて治療をおこないます。 - 【解釈的精神療法】
患者の症状や行動を解釈し、その背後にある心理的な意味を探求する治療法です。患者に自己理解を促し、問題の根本原因を見つけ出すことを目指します。
これらの心理療法で、精神的な安定や睡眠の質の向上が期待できます。
薬物療法
重度のうつ病や睡眠障害には、薬物療法が必要な場合があります。抗うつ薬や睡眠薬などの適切な使用は、症状の改善が期待できます。
ただし、それぞれの薬には一定の副作用やリスクが伴います。抗うつ薬の副作用は、口の渇きや便秘、頭痛などです。睡眠薬には、注意力の低下や記憶障害、立ちくらみなどの副作用があります。
睡眠薬に抵抗がある場合は、主治医に相談してみましょう。当医療法人の東京にある心療内科の「新宿うるおいこころのクリニック」では、薬物療法も含めた総合的な治療を提供していますので、患者さんの希望や症状に合った治療法をご提案します。薬の使用に関するご不安がある場合は、お気軽にご相談ください。
薬物療法による睡眠時無呼吸症候群への影響

睡眠薬や抗うつ剤などの薬物療法は、筋肉を弛緩させる作用があるため、気道が塞がりやすくなる可能性があります。これにより、睡眠時無呼吸症候群の症状が悪化する可能性があります。そのため、睡眠時無呼吸症候群を併発している患者さんが薬物療法を受ける場合は、医師とよく相談し、リスクと利益を考慮した上で治療方針を決定する必要があります。
いびきメディカルクリニックでは、睡眠時無呼吸症候群に関する相談や治療を専門としています。医師やスタッフが丁寧に対応し、患者さんの状態に合わせた最適な治療を提供しています。睡眠時無呼吸症候群と薬物療法の関連についても、適切な情報提供やアドバイスを行っていますので、安心して相談してください。
睡眠時無呼吸症候群の薬物療法については下記記事でも詳しく解説しています。併せてご覧ください。
うつ病と睡眠時無呼吸症候群の併発には専門医のいるクリニックの受診が重要
うつ病と睡眠時無呼吸症候群は相互に関連し合うことがあります。うつ病患者が睡眠障害を併発する理由や、薬物療法による睡眠時無呼吸症候群への影響など、専門的な知識が必要です。そのため、うつ病や睡眠時無呼吸症候群の治療を考えている方は、専門医のいるクリニックの受診をおすすめします。
うつ病や睡眠時無呼吸症候群は、放置すると重篤な症状を引き起こす可能性があります。早期に適切な治療を受けることで、症状の改善や合併症の予防が期待できます。うつ病や睡眠時無呼吸症候群に関する不安や疑問がある場合は、いびきメディカルクリニックなどの専門クリニックで相談を行い、適切な治療を受けることをお勧めします。
よくある質問
うつ病の患者さんが、睡眠薬や抗うつ剤を服用している場合、睡眠時無呼吸症候群を併発しやすい傾向にあります。なぜなら、睡眠薬や抗うつ剤は、筋肉を弛緩する働きがあり、舌や口蓋垂が気道を塞ぎやすいからです。