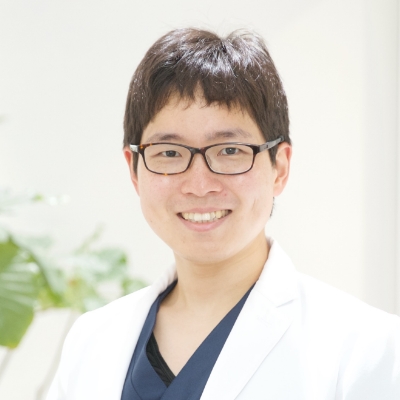レム睡眠とは?ノンレム睡眠との違いは? 良質な睡眠には2つのバランスが大切です

目次
私たちが日々の疲れを癒し、健康を保つために欠かせないもの、それが「睡眠」です。そして、睡眠の質を左右する要因として、「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」という2つの種類の睡眠が存在することをご存知でしょうか?
正常な睡眠は、これらの睡眠が交互に現れるサイクルで成り立っています。そして、それぞれの睡眠には重要な役割があり、それらの重要性を正しく理解することで、質の良い睡眠を手に入れるためのヒントが見えてきます。
本記事では、レム睡眠とノンレム睡眠の違いや、それぞれが果たす役割について詳しく解説していきます。
睡眠の仕組みとレム睡眠・ノンレム睡眠の基本

私たちが毎日必要な睡眠には、2つの重要な仕組みが関わっています。まずは、睡眠の基本的な仕組みについて解説します。
1つ目が、「睡眠欲求」です。覚醒中に体と脳を使い続けることで疲労が蓄積すると、自然と「眠りたい」という欲求が高まります。起きている時間が長いほど睡眠欲求は強くなり、一度眠るとこの睡眠欲求は急速に低下し、十分な睡眠を取ることで完全に消失します。そして、私たちは再び目覚めて日常生活を始めます。
2つ目が、「覚醒力」です。睡眠欲求に対して、日中私たちが活動できるのは「覚醒力」のおかげです。覚醒力は体内時計の働きによって調整され、交感神経の活性化や覚醒作用のあるホルモンの分泌、深部体温の上昇などが関与しています。この覚醒力は日中を通じて高まることで、強まる睡眠欲求に打ち勝って私たちを活動的にさせるのです。
しかし、夜になると睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌が始まることで急激に覚醒力が低下し、眠気が訪れます。この仕組みにより、私たちは1日の終わりに自然と寝つくことができるのです。
そして、睡眠は「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」という2つの異なる状態が繰り返されることで成り立っています。これらは、互いに補完し合いながら心身の健康を支える役割を果たしています。
レム睡眠とは?

レム睡眠とは浅い眠りの状態で、脳が活発に活動し、夢を見ることが多く、記憶の整理や感情の安定に関与するとされています。その内容を詳しく見ていきましょう。
レム睡眠は脳の活動が覚醒時に似ている
レム睡眠中は、体は休息していますが、脳は活発に働いている状態で、脳波は覚醒時に近い小刻みな波形を示します。また、閉じたまぶたの下で眼球が急速に動く「急速眼球運動(Rapid Eye Movement=REM)」が特徴で、この現象が「レム睡眠」という名称の由来となっています。
レム睡眠中の骨格筋の活動低下
レム睡眠中は骨格筋(自分で動かすことのできる筋肉)の活動低下が見られます。これは、レム睡眠には「身体を休める」という働きがあるためで、余計な筋肉の緊張を抑えることで、エネルギーを節約していると考えられています。
レム睡眠は夢を見ることが多い時間
レム睡眠には、夢を見ることが多いという大きな特徴があります。レム睡眠中の人を起こすと、多くの割合で「夢を見ていた」と答え、その内容も非常に鮮明で、ストーリー性のある夢が多いと言われています。
ただし、夢を見ることの理由については、記憶の整理をしているという説が有力ですが、明確な理由については未だ解明されていません。
夢について近年明らかになっていること
レム睡眠と夢の関係については新しい仮説も次々と提唱されています。
例えば、レム睡眠中に見られる「急速眼球運動」については、「見ている夢の像を追うために眼球がそちらに視線を向けているから」と言われています。
また、レム睡眠中の骨格筋の活動低下についても、睡眠中に夢と同じ行動をとらないように、脳がブレーキをかけている可能性が高いと言われています。
レム睡眠は感情の安定に関与する
レム睡眠は、「感情の安定」にも関与しています。
人間は生きているとさまざまな経験をしますが、時には辛いネガティブな経験をすることもあります。しかし、こうした負の記憶は、いつまでも鮮明に覚えていると、日常生活を送るうえで非常に強い足かせとなります。
レム睡眠時において、ネガティブな情動が残らないように怒りや悲しみ、恐怖といった負の感情を処理する過程で悪夢を見ると考えられています。
参考:
レム睡眠(れむすいみん)|e-ヘルスネット(厚生労働省)
どうして人は、訳の分からない夢を見るのか|日本経済新聞
夢の動きを追う目の動き〜日経サイエンス2010年10月号より|日経サイエンス
ノンレム睡眠とは?

ノンレム睡眠とは、脳と体の両方が休息している状態を指します。この状態では、体の修復や成長が促され、心身の回復に重要な役割を果たします。
ちなみに、ノンレム睡眠の名前は、「レム睡眠ではない」という意味の「non-REM」から来ています。どのような特徴・役割があるのか詳しく見ていきましょう。
ノンレム睡眠は身体の修復を助けて疲労を回復させる
ノンレム睡眠は身体だけでなく、脳(大脳)も休息しているとされています。
このタイミングでは、自律神経はリラックスするときに働く「副交感神経」が優位な状態で、心拍数や呼吸数、血圧も穏やかな省エネモードになっています。
実際、このタイミングで眠っている人を起こすと、非常に目覚めが悪く、「寝足りない」気分になることが多いとも言われています。これは、ノンレム睡眠は脳を休めて体をメンテナンスしている状態であり、起きる準備ができていないためです。
ノンレム睡眠は成長に欠かせない
「寝る子は育つ」という言葉通り、ノンレム睡眠中には成長ホルモンが分泌されます。
成長ホルモンは、その名の通り身体の「成長」に欠かせないホルモンで、骨の成長を促したり、筋肉を成長させたりなどが主な働きです。成長ホルモンはノンレム睡眠中、特に就寝後最初に現れるノンレム睡眠時に多く分泌されることがわかっています。
さらに、成長ホルモンには骨や筋肉の成長促進機能だけでなく、免疫系に働きかけて病気になりにくくしたり、脂肪を分解したり、脳の認知機能に関与したりなど、さまざまな作用ももたらします。このことから、ノンレム睡眠は子供や若者だけでなく、大人にとっても疲労を回復したり、健康で過ごしたりするためには重要な睡眠と言えます。
ノンレム睡眠は認知症の予防に役立つ
ノンレム睡眠は脳の老廃物を除去し、アルツハイマー型認知症の予防に寄与するとされています。
アルツハイマー型認知症の原因は、完全には解明されていませんが、アルツハイマー型認知症を発症した患者の脳では、「老人斑」と呼ばれる特徴的なシミが確認されます。さらにこの老人斑は、「アミロイドβ」というタンパク質、いわゆる脳の老廃物が原因で形成されることもわかっています。
認知症を防ぐためには、アミロイドβを脳から効果的に排出することが重要です。そして、この排出プロセスに深く関わっているのが、ノンレム睡眠です。
質の高いノンレム睡眠を十分に取ることは、脳の老廃物排出を促進し、結果的にアルツハイマー型認知症の予防につながる可能性があると指摘されています。この分野は現在も活発に研究が進められており、今後の発見が期待されています。
参考:
ノンレム睡眠(のんれむすいみん)|e-ヘルスネット(厚生労働省)
どうして早寝が体にいいの?東京都医師会
良質な睡眠をとって認知症を予防しよう!|独立行政法人 国立病院機構 東名古屋病院
レム睡眠とノンレム睡眠の違いとは?

レム睡眠とノンレム睡眠の違いは、脳の活動状態や身体の動き、果たす役割にあります。レム睡眠は脳が活発に働く一方で、ノンレム睡眠は脳と体が深く休息する時間です。 詳しく解説していきます。
レム睡眠とノンレム睡眠の違い①:脳の活動
レム睡眠とノンレム睡眠中の脳の状態に大きな違いがあります。
まず、レム睡眠中の脳は、覚醒時に近い状態にあります。脳波を見ると、レム睡眠中は高速で不規則な波形が観察され、この間に情報の整理や記憶の定着が行われていることを示しています。
一方、ノンレム睡眠中の脳は比較的穏やかで、休息モードに入っています。特に深いノンレム睡眠の段階では、脳波は低速で大きな波形を示し、「徐波睡眠」と呼ばれる状態になります。
この間、脳のエネルギー消費は抑えられ、体の修復に専念する時間となります。
レム睡眠は主に脳は活動していて体は休む時間であり、ノンレム睡眠は体だけでなく脳も休めることで、メンテナンスに集中していると言えるでしょう。
レム睡眠とノンレム睡眠の違い②:身体の動き
レム睡眠とノンレム睡眠では、身体の動きに明確な違いがあります。レム睡眠中は筋肉の動きがほぼ停止する一方で、ノンレム睡眠中は適度に筋肉が緊張しているのが違いです。
まず、レム睡眠中は「筋緊張抑制」という仕組みにより、骨格筋の動きがほぼ停止します。これにより、夢の中での行動が実際の身体に反映されないようになっています。ただし、眼球が急速に動く「急速眼球運動」や、呼吸や心拍の変動は見られます。
一方、ノンレム睡眠中は筋肉が適度に緊張しており、寝返りを打つなどの軽い動きが可能です。この時間帯は、副交感神経が優位になり、心拍数や呼吸が安定します。特に深いノンレム睡眠では、体温が低下し代謝が抑制されることで、身体のエネルギーが節約されます。
このように、レム睡眠とノンレム睡眠の身体の動きに関する違いは、それぞれの役割や目的に応じた特性であり、どちらも質の良い睡眠を得るために重要な要素となっています。
レム睡眠とノンレム睡眠の違い③:役割の違い
レム睡眠とノンレム睡眠には、それぞれ異なる役割があります。レム睡眠は主に脳の記憶や感情の整理を行い、ノンレム睡眠は身体の修復やエネルギーの回復を担っています。
レム睡眠は、夢を見ることで、記憶や感情の整理をしていると言われています。特に、感情の整理はストレスや不安を和らげ、心のバランスを保つために重要とされています。
対して、ノンレム睡眠は、身体の修復や成長、エネルギーの回復に欠かせない時間です。この間、成長ホルモンが分泌され、細胞の修復や免疫機能の強化が進行します。さらに、脳内の老廃物の除去も行われ、脳の健康維持に貢献します。
このような役割の違う両者がバランスよく補完し合うことで質の良い睡眠が成り立っています。
参考:
レム睡眠(れむすいみん)|e-ヘルスネット(厚生労働省)
ノンレム睡眠(のんれむすいみん)|e-ヘルスネット(厚生労働省)
レム睡眠とノンレム睡眠の睡眠サイクルの変化

私たちの睡眠は、レム睡眠とノンレム睡眠が約90分間隔で交互に繰り返されるサイクルで構成されています。このサイクルは一晩の間に4〜6回繰り返され、時間が経つにつれてその構成に変化が見られます。
入眠直後には、深いノンレム睡眠が優勢となり、この時間帯に身体の修復や成長が集中して行われます。その後、浅いノンレム睡眠を経てレム睡眠へ移行します。一晩の間で最初に現れるレム睡眠は短時間で終わることが多いですが、朝が近づくにつれて徐々にレム睡眠の割合が増加します。これにより、目覚める直前の時間帯には、レム睡眠が多くを占めるサイクルとなります。
このように、睡眠のサイクルは時間帯によって変化し、夜間の初期には体の回復が、朝に近づくにつれて脳の整理が重点的に行われる仕組みになっています。
睡眠の質を高めるにはレム睡眠とノンレム睡眠のバランスが重要
睡眠の質を決める鍵は、レム睡眠とノンレム睡眠のバランスです。これらの睡眠は互いに補完し合い、心身の健康を支える重要な役割を担っています。
睡眠が始まると、まず深いノンレム睡眠の段階に入ります。この時間帯は次のような働きを担います。
- 身体の修復:筋肉や細胞の再生が促進され、免疫力が強化される。
- エネルギーの回復:日中に消費されたエネルギーを補充する時間。
- 成長ホルモンの分泌:成長に重要で、特に子供や若者の成長を支えるほか、大人でも代謝や免疫機能の維持に寄与する。
- 脳の老廃物の除去:脳に溜まった老廃物を除去することで、認知症を発症するリスクを下げる。
そして、朝が近づくにつれて、レム睡眠の割合が増加し、以下のようなプロセスが進行します。
- 記憶の整理と定着:レム睡眠中、脳は日中に得た情報を整理し、記憶として定着させる。
- 感情の調整:ストレスや不安といった感情を整理し、精神的な安定を保つ。
これらの睡眠がバランス良く存在することで、私たちは翌朝、心身ともにリフレッシュされた状態で目覚めることができます。朝起きた時に感じる「熟睡感」は、この2つの睡眠が適切な比率で繰り返されている証拠です。質の高い睡眠を得るためには、このサイクルを乱さない生活習慣が重要です。
睡眠の質のバランスが崩れる原因は生活習慣の乱れとストレス

質の高い睡眠には、レム睡眠とノンレム睡眠のバランスが欠かせませんが、そのバランスを乱すのが、生活習慣の乱れとストレスです。ここでは、生活習慣の乱れとストレスがどのようにして睡眠の質のバランスを乱すのかについて詳しく解説します。
生活習慣の乱れが睡眠の質にもたらす影響
生活習慣の乱れは、体内時計を乱し、睡眠の質を著しく低下させます。
体内時計は、脳内の「視交叉上核」という部位が司っており、光の刺激を受けてリズムを調整します。しかし、夜更かしや起床時間が一定しない生活が続くと、リズムが狂い、睡眠サイクルが正常に働かなくなります。その結果、疲労回復が正しく行われず、夜間の不眠や日中の眠気、強い倦怠感を覚えるようになります。
ストレスが睡眠の質にもたらす影響
強いストレスは、自律神経のバランスを崩し、睡眠の質を低下させます。
ストレスが高まると、自律神経のうち交感神経が優位になり、体が常に「戦闘モード」のような状態になります。この状態では、心拍数や血圧が上昇し、体がリラックスしづらくなります。
また、たとえ眠れたとしても、ノンレム睡眠が短くなってレム睡眠が長くなることで、些細な物音で目が覚めるようになったり、睡眠時間を確保していても寝足りない状態になったりします。
さらに、睡眠不足や質の低下はストレスをさらに増大させ、悪循環に陥ることがあります。
いびきや睡眠時無呼吸症候群(SAS)は睡眠の質に影響する
いびきは、睡眠中に気道が狭くなることで発生します。軽度であれば大きな問題はありませんが、重度のいびきは呼吸を妨げて睡眠の質を低下させます。
さらに、いびきが慢性化すると「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」を発症することがあります。睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、酸素不足を引き起こし、心臓や血管に負担をかけるだけでなく、日中の集中力低下や疲労感を招きます。放置すると高血圧や心疾患、うつ病などのリスクが高まるため、適切な治療が必要です。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)については下記記事で詳しく解説しています。併せてご覧ください。
レム睡眠とノンレム睡眠それぞれが不足するとどうなる?

レム睡眠が不足すると、記憶力が低下したり、ストレスや不安を感じやすくなったりします。一方、ノンレム睡眠が不足すると、疲労が回復しにくくなったり、集中力が低下したります。これらの内容について、より詳しく見ていきましょう。
レム睡眠が不足した場合
レム睡眠は、日中に得た情報を整理し、記憶として定着させる役割を担っています。そのため、レム睡眠が不足すると、記憶の定着がうまくいかず、学習した内容を思い出しにくくなったり、新しいスキルの習得が困難になることがあります。
また、レム睡眠は夢を見ることで、感情を整理し、心のバランスを保つ働きを持っています。不足すると、感情の整理が適切に行われないため、イライラしやすくなったり、不安やストレスを過剰に感じるようになることがあります。
参考:
睡眠と記憶に関する近年の知見|鈴木 博之(国立精神・神経センター精神保健研究所 精神生理部)
ノンレム睡眠が不足した場合
ノンレム睡眠中には、成長ホルモンが分泌され、細胞の修復や免疫システムの強化が行われます。この段階が不足すると、細胞修復や免疫強化が正しく行われないので、怪我の治りが遅くなったり、感染症にかかりやすくなるといった問題が生じます。
さらに、ノンレム睡眠中には、脳内の老廃物が排出されるとされています。これが不足すると、アルツハイマー病の原因とされるアミロイドβなどが蓄積しやすくなる可能性があります。そのため、ノンレム睡眠不足は長期的な脳の健康にも悪影響を及ぼします。
レム睡眠とノンレム睡眠のバランスが質の良い睡眠のカギ

レム睡眠とノンレム睡眠は、それぞれが異なる役割を担いながら、心身の健康を支えています。どちらか一方が不足するだけでも、記憶力や感情、体の修復機能に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
質の良い睡眠を確保するためにも、生活習慣や睡眠環境を見直すことで、レム睡眠とノンレム睡眠のバランスを維持していきましょう。
よくある質問
はい、いびきや睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、睡眠サイクルを乱し、レム睡眠やノンレム睡眠の質を低下させる可能性があります。これが長期間続くと、健康リスクが高まるため、専門医に相談することをおすすめします。