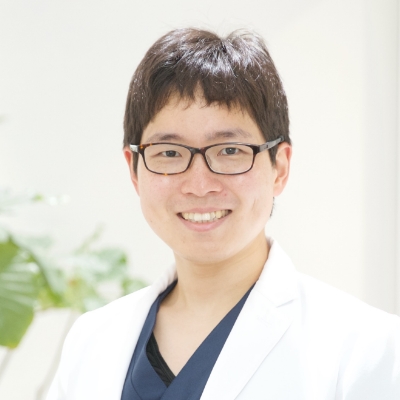早朝覚醒とは?朝早く目が覚める原因・対策・治し方まで一挙解説!
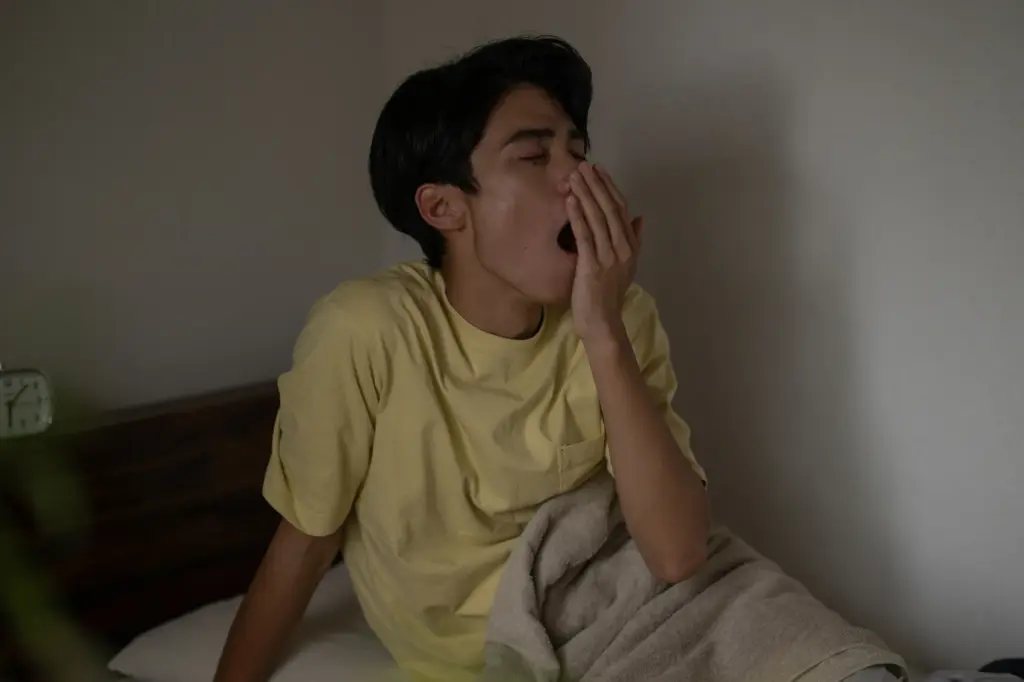
目次
早朝覚醒とは、予定より著しく早く目が覚めてしまい、そのまま眠れなくなってしまう状態のことです。十分な睡眠時間が確保できないため、日中の眠気や集中力低下など、生活の質に大きな影響を及ぼす可能性があります。早朝覚醒の背景には、睡眠時無呼吸症候群やうつ病といった病気が潜んでいることもあれば、ストレスや生活習慣の乱れが原因かもしれません。
この記事では、早朝覚醒の原因や特徴、そして改善のための対策について、医学的な観点から詳しく解説します。つらい症状でお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
早朝覚醒とは?
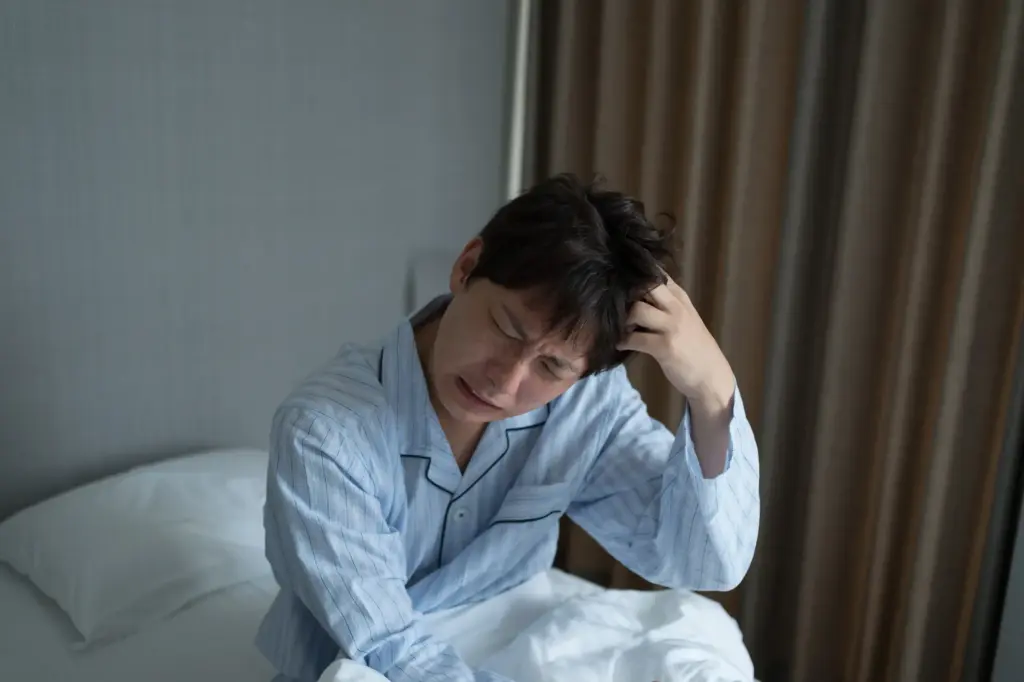
早朝覚醒は、十分な睡眠時間を取れないまま、予定よりおおよそ2時間以上早く目が覚めてしまい、その後眠れなくなる状態を指します。単なる美徳とされる「早起き」とは異なり、睡眠不足による心身への悪影響を伴う症状です。朝型の生活リズムで早めに起床する習慣は健康的である一方、早朝覚醒では必要な睡眠時間が確保できず、日中の活動に支障をきたします。
参考:
救心製薬「現代人と睡眠:不眠の種類と原因を知りましょう」
早朝覚醒による影響
慢性的な睡眠不足により、日中の強い眠気や集中力の低下が生じます。記憶力や判断力も低下し、仕事や学業のパフォーマンスに影響を及ぼします。また、疲労が蓄積されやすいためイライラや不安感が強まりますが、心配になるのは、メンタルヘルスの悪化です。長期化すると、免疫力の低下や生活習慣病のリスク上昇も懸念されます。
早朝覚醒の特徴
早朝覚醒の特徴は、早朝に一度目が覚めると、再び眠ることが困難になります。目覚めた後は、頭がクリアで眠気を感じにくい状態が続きますが、午前中から強い眠気に襲われることが特徴的です。また、夜間の入眠には問題がないことが多く、むしろ疲労感から早めに就寝する傾向がみられます。
朝早く目が覚めてしまう…早朝覚醒の主な原因とは?

早朝覚醒には様々な要因が関係しています。睡眠時無呼吸症候群やうつ病などの疾患が背景にあることも少なくありません。また、ホルモンバランスの乱れやストレス、生活習慣の乱れなども大きな影響を与えている可能性もあります。これらの原因を理解することが、適切な対策を講じる第一歩となります。
早朝覚醒の原因①:睡眠時無呼吸症候群
睡眠時無呼吸症候群では、睡眠中に呼吸が止まることで血中酸素濃度が低下し、深い睡眠が得られにくくなっています。この無呼吸状態から回復するために体が覚醒してしまうため、早朝に目が覚めやすくなるのです。特に、いびきが激しい、日中の眠気が強いといった症状を伴う場合は要注意です。早期に専門医を受診して、適切な治療を受けることをおすすめします。
睡眠時無呼吸症候群の詳細は下記記事をご覧ください。
早朝覚醒の原因②:うつ病
うつ病における特徴的な睡眠障害の一つが早朝覚醒です。セロトニンなどの神経伝達物質の働きが低下するために、睡眠・覚醒リズムが乱れてしまうのです。また、早朝に目が覚めた際に不安や悲観的な考えが強まり、再入眠を一層困難にしていることもあります。気分の落ち込みや食欲不振などの症状も併せて感じる場合には、精神科や心療内科への相談を検討する必要があるでしょう。
うつ病は精神に関わる病気です。詳しくは下記記事をご覧ください。
早朝覚醒の原因③:ホルモンバランスの乱れ
体内時計の調節に関わるホルモンバランスが崩れると、睡眠リズムに大きな影響が生じることになります。特に、睡眠を促すメラトニンや、覚醒に関わるコルチゾールの分泌リズムの乱れは、早朝覚醒の重要な要因です。加齢や生活習慣の乱れによっても、これらのホルモンバランスは変化していきます。
更年期
更年期には女性ホルモンの急激な変動が起こるため、不眠や早朝覚醒といった睡眠障害が生じやすくなります。特に、エストロゲンの減少は睡眠の質に大きく影響を与えており、ホットフラッシュ(ほてり・のぼせ)による夜間の目覚めも睡眠を妨げる要因となっているのです。この時期には、生活習慣の改善に加えて、症状に応じてホルモン補充療法なども検討する必要があります。
早朝覚醒の原因④:ストレス
過度なストレスは、自律神経系のバランスを崩し、質の良い睡眠を妨げる可能性があります。仕事や人間関係の悩み、将来への不安などにより、早朝に目が覚めると心配事が頭をめぐり、再び眠れなくなってしまうのです。また、ストレスによって体内時計をつかさどる神経伝達物質の分泌も乱れやすく、これが早朝覚醒を引き起こす原因となることもあります。
早朝覚醒の原因⑤:乱れた生活習慣
不規則な生活リズムは、体内時計を狂わせる大きな要因となりえます。特に、就寝時間や起床時間が一定でないことは、睡眠の質を低下させる原因となるでしょう。
不規則な生活時間
不規則な生活時間は、体内時計の乱れを引き起こす主要な原因となりえます。就寝時間や起床時間が一定でないことで、体内時計は正常なリズムを保つことができなくなるのです。特に、休日に平日と大きく異なる時刻で生活するのは、「社会的時差ぼけ」と呼ばれる状態を引き起こし、睡眠の質を低下させます。また、夜更かしや昼寝の取り方によっても、深夜や早朝に目が覚めやすくなってしまうでしょう。
過度なアルコール摂取
寝酒としてアルコールを摂取することは睡眠に良いように感じられますが、後半の深い眠りの減少や利尿作用によって、早朝に目が覚めやすくなってしまうのです。就寝前のアルコール摂取は控えめにしましょう。
早朝覚醒の原因⑥:生活環境
快適な睡眠には適切な環境作りが欠かせません。室温が高すぎたり低すぎたりすると、体温調節が難しくなり、睡眠が妨げられることになります。また、湿度が低いと喉の渇きで目が覚めやすくなるでしょう。早朝の光や騒音も睡眠を妨げる要因となっています。特に、家族の生活音は、無意識のうちに脳を覚醒させてしまうので、何らかの対策を取るのをおすすめします。
早朝覚醒になりやすい人の特徴

以下のような人が、早朝覚醒を起こしやすいでしょう。
- 完璧主義的な性格の人
- 責任感が強く仕事熱心な人
- 不安や心配が多い人
- ストレス解消が苦手な人
完璧主義的なのはしっかり実行したい気持ちの表れであり、責任感が強いのも仕事の上では良いこととして発揮されますが、どうしてもストレスが溜まりがちになってしまうものです。心配事や過度なストレスは自律神経系のバランスを乱してしまう可能性があります。また年齢的には40代以降の人、特に更年期を迎える女性は、ホルモンバランスの変化も加わって症状が現れやすくなっています。こうした特徴を持つ人は、早めに対策を講じることが望ましいでしょう。
早朝覚醒の治し方

早朝覚醒の治療においては、原因となっている疾患や状態に応じた適切なアプローチが重要です。特に睡眠時無呼吸症候群が原因の場合、専門医による適切な診断と治療が必要不可欠です。また、うつ病や更年期障害が背景にある場合には、それぞれの症状に応じた治療をすることで、早朝覚醒の改善も期待できます。
早朝覚醒の治し方①:いびき治療
いびきは睡眠中に鼻や口から肺までの空気の通り道「気道」が狭くなるために発生します。気道が狭くなり息を吸うときに空気の通過部分で振動が起き、音が発生するのです。
治療方法は気道が狭くなる原因によって違いますが、代表的なものは以下のとおりです。
- CPAP(シーパップ)療法やマウスピース
- 口蓋垂や軟口蓋の切除
- 従来のいびきレーザー治療(ナイトレーズ)
- 最新いびきレーザー治療(パルスサーミア)
CPAP(シーパップ)療法は就寝時に専用のマスクを装着し、圧力のかかった空気を送り込むことで、気道の閉塞を防ぐというものです。口蓋垂などの形状に異常がある場合にもいびきは発生します。メスを使った手術の他に、レーザー治療という選択肢もあります。いびきの程度や生活スタイルに合わせて、最適な治療法を選択していくことが大切です。
いびきメディカルクリニックでは、最新いびきレーザー治療(パルスサーミア)を使用しています。当院オリジナルのいびきレーザー治療ですので、気になる方は下記をチェックしてみてください。
<いびきメディカルクリニックオリジナルのいびきレーザー治療「パルスサーミア」の詳細はこちら>
早朝覚醒の治し方②:薬物治療
うつ病による早朝覚醒には、抗うつ薬による治療が効果的です。特に、睡眠を改善する作用を持つ薬剤を選択することで、早朝覚醒の症状も改善が期待できます。
更年期障害によるホルモンバランスの乱れが原因の早期覚醒の場合は、女性ホルモンの急激な減少が原因の症状なので、そのままでも次第に落ち着くでしょう。しかし、症状が辛い場合には、早めに医師に相談しましょう。更年期障害の方の薬物治療としては、ホルモン補充療法などがあります。
早朝覚醒しないための対策

早朝覚醒を防ぐためには、睡眠環境の整備と生活習慣の改善が重要です。特に、寝室の環境整備や、食事・運動といった基本的な生活習慣の見直しが効果的です。また、就寝前のリラックスタイムを確保すると、質の良い睡眠につながっていくでしょう。
早朝覚醒の対策①:睡眠に適した環境を整える
快適な睡眠のためには、適切な睡眠環境を整えることが不可欠です。温度、光、音などの環境要因に注意を払いましょう。
寝室にはスマホを持ち込まず、できるだけ暗くする
就寝前のスマートフォンの使用は、ブルーライトの影響で睡眠を妨げる原因となります。また、SNSやメールのチェックは心理的な興奮を引き起こし、良質な睡眠の妨げとなってしまいます。寝室は可能な限り暗くし、カーテンやブラインドで外光をしっかりと遮断することが望ましいでしょう。日中に光を多く浴びると夜間の照明の光による悪影響が減少すると報告されているので、1日を通して光環境を整えるのは、良質な睡眠確保のために重要です。
寝室は暑すぎず寒すぎない温度にする
快適な睡眠には適切な室温管理が欠かせません。冬に実施した調査研究から「就寝前に過ごす部屋の室温が低いと入眠に時間がかかる」、夏の寝室の室温上昇時に「睡眠時間が短縮し、睡眠効率が低下する」ことが報告されています。つまり、暑すぎても寒すぎてもダメ。寝具の調整と合わせて、エアコンや暖房器具を活用しながら、快適な温度環境を保っていくことが大切です。また、湿度も40~60%程度に保つことで、喉の渇きによる中途覚醒を防げるでしょう。
できるだけ静かな環境にする
外部からの騒音は、睡眠の質に大きな影響を与えます。騒音によって目覚める頻度が増加し、深い睡眠が減少する結果が報告されているので、可能な限り静かな環境を確保し、必要に応じて耳栓やホワイトノイズを活用することも検討しましょう。
また、寝室の扉や窓の防音対策、カーテンの工夫なども効果的です。騒音に対する感受性には個人差があります。家族との生活音についても話し合い、お互いの睡眠を妨げない工夫を考えることが大切でしょう。
早朝覚醒の対策②:食事や運動の生活習慣を整える
健康的な睡眠のためには、日中の活動から夜間の過ごし方まで、生活習慣全体を見直すことが大切です。適度な運動と規則正しい食事が、質の良い睡眠につながります。
適度な運動習慣を身につける
適度な運動は、深い睡眠を促進する効果があります。ただし、就寝直前の激しい運動は逆効果となるため、夕方までに終えることが望ましいでしょう。ウォーキングやストレッチなど、自分に合った運動を定期的に行うことで、自律神経のバランスが整い、睡眠の質も向上していきます。また、日中の活動量を増やすことが、夜間の良質な睡眠につながります。
しっかり朝食を摂り、就寝直前の夜食を控える
朝食をしっかり摂ることは、体内時計を整える重要な要素となります。一方、就寝直前の食事は消化活動を活発にし、睡眠の質を低下させる原因となります。夕食は就寝の2~3時間前までに済ませ、その後の夜食は控えめにしましょう。特に、脂質や糖質の多い食事は、深い睡眠を妨げる要因となります。
過度なアルコール摂取を控える
寝酒は一時的に寝つきを良くする効果はあるものの、睡眠の質を著しく低下させます。アルコールの影響で中途覚醒や早朝覚醒が起こりやすくなり、結果として十分な休息が得られなくなってしまうのです。また、頻尿や脱水による喉の渇きも良質な睡眠を妨げます。休肝日を設けるなど、適度な飲酒を心がけることが大切です。
就寝前にリラックス
就寝前のリラックスタイムは、質の良い睡眠への準備として重要です。入浴やストレッチ、呼吸法などでリラックスすることで、自律神経が副交感神経優位となり、睡眠への準備が整います。また、読書や静かな音楽を聴くなど、自分に合ったリラックス方法を見つけることが大切です。ただし、興奮を誘うような活動は避けましょう。
早朝覚醒の対策と合わせて、睡眠の質を上げる方法を試したい方は下記記事をご覧ください。
参考:
「健康づくりのための睡眠ガイド2023」|厚生労働省
早朝覚醒にお悩みならいびきメディカルクリニックにご相談ください
早朝覚醒の背景には、睡眠時無呼吸症候群などの疾患が潜んでいることがあります。まずは当クリニックに相談することから始めてみませんか。豊富な治療実績に基づいて、一人ひとりの状況に応じた、適切な治療法を提案いたします。無料カウンセリングもしていますので、ご希望の方はwebやお電話、LINEにて予約してください。
よくある質問
一般的に、予定の起床時刻より2時間以上早く目が覚めてしまい、その後眠れない状態を早朝覚醒と呼びます。ただ時刻だけでなく、十分な睡眠時間が確保できていないことや、日中の活動に支障をきたすことも重要な判断基準です。早起きが習慣で、日中の活動に問題がない場合は、早朝覚醒ではありません。心配な場合は、専門医へ相談しましょう。